| その他の特集(2011年) | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
||||||||||||||
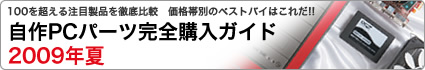 |
||||||||||||
| TEXT:鈴木雅暢 | ||||||||||||
| 最新スタイルを先取りせよ! | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
 2009年を迎えてから早半年が過ぎようとしている。この間のPC自作市場は、比較的淡々と経過したような印象もあるが、改めて振り返ってみると製品の顔ぶれや価格などが大きく変化している分野も少なくない。 2009年を迎えてから早半年が過ぎようとしている。この間のPC自作市場は、比較的淡々と経過したような印象もあるが、改めて振り返ってみると製品の顔ぶれや価格などが大きく変化している分野も少なくない。なかでも情勢が変化しているのがCPU。45nmプロセスルールの導入でIntelに後れを取っていたAMDが、Phenom II、そして新ソケットのSocket AM3をリリースして攻勢に転じた。6月に入ってからは低消費電力版を含めて一気にラインナップを拡充し、ハイエンドのみならず、ミドルレンジ、ローエンドまでSocket AM3/45nmプロセスルール製品で揃えてきた。IntelのほうもCore 2 Quadの低消費電力版、Core i7の新モデルを投入するなど動きを見せており、にわかに活気付いてきている。 そして、その影響を大きく受けているのがメモリだ。Core i7、Socket AM3版CPUの本格化によってDDR3メモリの需要が増加。価格も下がってきており、DDR2からの世代交代がいよいよ近い雰囲気だ。とくにメーカー製の2枚組、3枚組セット品の価格差は確実に縮まっている。この秋にはIntelからいよいよメインストリーム向けの新CPUがリリースされることが判明しており、DDR3メモリの需要はさらに加速しそうだ。 |
||||||||||||
|
||||||||||||
 Socket AM3が登場 Socket AM3が登場AMD CPU用の新ソケットとしてDDR3メモリに対応するSocket AM3が登場。Socket AM2とはピン配置が異なっており、Socket AM2(AM2+)のCPUは使うことができない |
||||||||||||
 いよいよDDR3の時代到来 いよいよDDR3の時代到来IntelのCore i7に続き、AMDがSocket AM3のラインナップを揃えてきたことでDDR3メモリの需要が増してきた。価格下落も順調で、世代交代の気配が濃厚になってきた |
||||||||||||
 急ピッチでSSDの世代交代が進む 急ピッチでSSDの世代交代が進むほんの数年前、PCのメインストレージとしてフラッシュメモリを使う時代の到来を予想していたユーザーがどれだけいただろうか。PCI Express接続製品が登場するなどSSDの進化はとどまることを知らない |
||||||||||||
 HDDはより大容量化 HDDはより大容量化一方のHDDはアクセス速度ではSSDにかなわないものの、フルHD時代のデータ保存用としては欠かすことができない。2TBクラスの製品も数を増やしてきており、適材適所で使い分けるのが最新のスタイル |
||||||||||||
|
||||||||||||
| SSDの動きからも目が離せない。大容量DRAMキャッシュを内蔵したSSDが出揃い、新しいステージに入ったと言えるだろう。2.5インチサイズのSSDマウンタなども多く見かけるようにもなってきた。HDDの大容量化、低価格化も順調に進んでいる。これからPCを自作するなら、システムはSSDに、データはHDDにと、SSDとHDDを併用するというスタイルは当然検討すべきだろう。 これからのスタイルという面では、フルHDというキーワードも挙げられる。BDドライブや高画素デジタル一眼レフカメラ、フルHD対応デジタルビデオカメラなども完全に普及期に入っており、PCでHDコンテンツを取り扱う機会は確実に増えてきた。フルHDコンテンツを前提にパーツを選びたいところだ。 それに関連して、GPUのパワーを3D描画性能以外の汎用的な用途に活用しようというGPGPUのアプローチがある。1年ほど前までは「おまけ」の範囲を超えるものではなかったが、ここに来て動画系を中心にクリエイティブ系アプリケーションでは積極的に活用されはじめており、さらにOpenCL、DirectX Compute Shaderなど、GPUをより効果的に利用しようという取り組みも始まっている。これからはより重要視する必要がある。 |
||||||||||||
|
||||||||||||
 『フルHD』 『フルHD』BDドライブ、フルHDビデオカメラに続き、フルHD解像度をサポートする液晶ディスプレイが低価格化、急速に普及している。今後のPCにはHDコンテンツを扱うパワーは必須だろう |
||||||||||||
 『GPGPU』 『GPGPU』GPUのパワーを3D描画以外の汎用的な用途に応用するGPGPUのアプローチが本格化してきた。動画エンコード、ビデオ編集の特殊効果などを高速に行なうことができるアプリケーションが次々と登場している |
||||||||||||
 『80PLUS認証』 『80PLUS認証』電源ユニットの高変換効率の証として定着した「80PLUS」マーク。信頼できる静音電源の目安として定着しており、ハイエンドでは上位の「80PLUS Silver」認証を取得する製品も増えている |
||||||||||||
|
||||||||||||
| 自作PCの伝統的な静音というテーマも依然として健在だ。CPUクーラーのヒートパイプや大型化、PCケースの天面排気、電源ユニットの80PLUS認証などさまざまなトレンドを生み出し、各パーツを進化させてきた。これからPC自作をするなら、2009年6月現在のトレンドはぜひチェックしておきたい。 そして、この先にはMicrosoftの次世代OS「Windows 7」の登場が控える。より進化したユーザーインターフェースに加え、SSDのサポートや、ビデオまわりの機能強化も注目されており、当然新OSを今から強く意識すべきだろう。 本特集ではPCパーツそれぞれの現状を手早く把握できるよう、ジャンルごとにトレンドを整理しつつ、価格帯別に主流製品を紹介していく。Windows 7やIntelの新しいCPUが今秋に登場するなら、それまで待ってPCを自作したほうがよいのではないか、そう思う方もいるだろう。確かにそれも悪くないが、この機会に各パーツの現状と今後の傾向を把握しておくことは、いざ“そのとき”に賢い選択をするために、きっとムダなことではないはずである。 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
サイト内検索
DOS/V POWER REPORT 最新号
-

-
DOS/V POWER REPORT
2024年冬号発売日:12月28日
特別定価:2,310円
書籍(ムック)

-
PC自作・チューンナップ虎の巻 2023【DOS/V POWER REPORT特別編集】
発売日:2022/11/29
販売価格:1,800円+税

-
このレトロゲームを遊べ!
発売日:2019/05/29
販売価格:1,780円+税

-
特濃!あなたの知らない秋葉原オタクスポットガイド
発売日:2019/03/25
販売価格:1,380円+税

-
わがままDIY 3
発売日:2018/02/28
販売価格:980円+税

-
忍者増田のレトロゲーム忍法帖
発売日:2017/03/17
販売価格:1,680円+税

-
楽しいガジェットを作る いちばんかんたんなラズベリーパイの本
発売日:2016/09/23
販売価格:2,400円+税

-
DVDで分かる! 初めてのパソコン自作
発売日:2016/03/29
販売価格:1,480円+税

-
ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』2
発売日:2015/12/10
販売価格:1,280円+税

-
髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 風雲編
発売日:2015/06/29
販売価格:2,500円+税

-
髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 怒濤編
発売日:2015/06/29
販売価格:2,500円+税

-
わがままDIY 2
発売日:2015/02/27
販売価格:980円+税

-
ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』
発売日:2014/12/05
販売価格:1,280円+税
-

-
わがままDIY 1
発売日:2011/12/22
販売価格:980円+税
アンケートにお答え頂くには「CLUB IMPRESS」への登録が必要です。
*プレゼントの対象は「DOS/V POWER REPORT最新号購入者」のみとなります。
ユーザー登録から アンケートページへ進んでください

 Windows Vistaの後継OSとしてMicrosoftが開発を進めているWindows 7の米国での発売日が2009年10月22日に決定した。日本でも同時期に発売されると見込まれている。
Windows Vistaの後継OSとしてMicrosoftが開発を進めているWindows 7の米国での発売日が2009年10月22日に決定した。日本でも同時期に発売されると見込まれている。
