
イチから自作するには時期が悪い? ならば今あるPCを強化しよう
Sandy Bridgeこと第2世代のCore iシリーズに対応したIntel 6シリーズチップセットのリコールにより、Sandy Bridge対応マザーボードはすべて販売が停止された。Sandy Bridgeで自作をしようとしていた人も多いだろうが、それはしばらくできなくなってしまった。
Sandy Bridgeの見せたパフォーマンスが素晴らしかっただけに、それがなくなってしまった影響は大きい。今手に入るシステム構成だけでは盛り上がりを欠くのは否めない。
そこで、アップグレードである。新しいPCを作るタイミングでないのであれば、パーツ単位で追加交換できるという自作PCならではのメリットを活かして今あるPCの性能や機能を部分的に強化し、延命させようというわけだ。
パーツ単位で性能や機能を強化 まずは今の構成を把握しよう
アップグレードを行なうにあたっては、今のPC構成をしっかり把握することが先決だ。すんなりいく場合も多いがシステム構成によっては何らかの壁に直面する場合もある。
というのも、アップグレードは基本的にはベースとなるシステムが古ければ古いほど大きな効果があるが、古いシステムと現行製品ではソケットやスロットの規格の互換性がない場合がある。そして、PCパーツ市場では現行規格でなくなってしまったものは割高になる傾向がある。古い規格のパーツを探して交換しても、コストのわりに性能がそれほど向上しないという効率の悪いアップグレードになってしまう。逆に、規格の問題はなくてもまだ自作してから期間が経っていないシステムなら性能向上の効果は小さいだろう。
では、今あるPCがどんなシステムならば効率のよいアップグレードが可能なのだろうか。考えてみたのが、冒頭のリストである。効果や効率の感じ方については人それぞれ差があるだろうが、客観的に見て、これらの項目に該当していれば、アップグレードを検討する価値は十分あると言える。
本特集では、世代別の代表的な構成を例に、効果的だと考えるアップグレードプランを提案し、ベンチマークテストなどによってその効果を紹介していく。環境によっては、大掛かりな入れ換えをしなくとも、見違えるような快適なシステムに生まれ変わる可能性もある。
低予算アップグレードの狙い目は?
CPU
最近のIntel CPUはCPUパッケージ/ソケットの仕様が多様化している上、相互に互換性がないため、旧世代からの効率的なアップグレードはしにくい。一方、AMD CPUのCPUパッケージ/ソケット仕様は下位互換性を考慮して進化しているため、かなり融通が利く。1世代前のSocket AM2+、さらに前のAM2対応マザーボードでも現行のSocket AM3対応CPUが使える製品がある。

AMDのCPUは互換性が高く、アップグレードには都合がよい。現行のSocket AM3対応CPUが使える旧世代のマザーボードは多い
メモリ
十分な容量のメモリを搭載していないならメモリの増設も比較的低コストで効果的な手段だ。もともとの容量が少ないほど効果が大きい。画像やビデオの編集などをやるならいくらあってもよいが、通常用途ならWindows XPで2GB、Windows 7なら3~4GBが快適に利用できる目安だろう。少し持て余し気味ならRAMディスクを作って活用するという手もある。
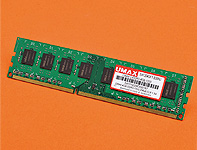
DDR3が主流になったことで1世代前のDDR2は底値から少し上昇傾向にある。今後はさらに上昇が予想されるため、増設するなら今のうちだ
HDD/SSD
体感での効果が大きく、さらにその後のツブシも利きやすいのがストレージのアップグレードだ。ランダムアクセスの高速なSSDをシステムドライブにすると、日常操作の体感レスポンスがグッと向上するし、HDDもデータドライブとして使うことができてムダがない。また、近い将来Sandy Bridgeなどで新しいシステムを導入する際に使い回すことも可能だ。

高価なイメージがあるSSDだが、体感速度向上の効果は抜群。小容量なら比較的買いやすい。HDDとうまく併用しよう
最新インターフェース
USB 3.0やSerial ATA 6Gbpsといった高速インターフェースがここ1年ほどで一気に普及してきた。こういった高速インターフェースや対応ドライブの導入も手軽で効果的なアップグレードと言える。マザーボードの新製品はほとんどが対応しているが、非対応の製品でもPCI Expressスロットに挿すインターフェースカードで簡単に追加できる。

Serial ATA 6GbpsやUSB 3.0は拡張カードで簡単に追加可能。両方をまとめて拡張できるカードもある
プランと効果を検討した上で自分に合った自作計画を
「アップグレードなんてしなくとも少しガマンして待っていればよい」と考える人もいるかもしれない。確かにそれも一つの考えだ。
ただ、今の時点でシステムに不満があり、あまりコストをかけずに効率的な強化ができるのであれば、当面それでしのぎつつ、半年くらいのスパンで状況を見たほうが、新規自作のタイミングを冷静に判断できると考えることもできる。
もちろん、アップグレードすることで満足度の高いシステムになるのであれば、当面と言わず1年2年、長く使えるようになるし、それに越したことはないだろう。実際に行なうかどうかは別にして、今後のアップグレード、あるいは新規自作の計画を立てる判断材料の一つとして活用していただければ幸いである。

















