最新の電源はここがスゴイ!
高効率

高変換効率の証明である80PLUS認証は低価格製品にも広く普及。最高90%の効率を誇る80PLUS Goldの基準を満たす製品も多く登場してきた
大出力

ハイエンド製品では1,000Wを超える大出力もめずらしくない。また、+12V系は1系統にまとめられ、80A以上の出力を備える製品が増えている
高品質

品質面もさらに向上。寿命に影響するコンデンサに、熱に強い固体コンデンサを採用する製品もある
進化を続ける電源ユニット 最新の電源仕様に対応
電源ユニットは、CPUやビデオカード、マザーボード、HDDなど、PCシステムを構成するそれぞれのPCパーツに電力を供給する役割を持つパーツだ。PCパーツは+12V、+5V、+3.3Vといった低い電圧の直流を利用して動作するが、一般家庭のコンセントから供給される電流は、一定周期で電圧が変動する交流で、電圧も100Vと高い。電源ユニットの役割は、この交流を直流に変換し、電圧を調整してそれぞれのパーツへ供給することにある。
この役割は現在のPCの前身であるPC/AT(IBMが発売したパーソナルコンピュータ)の時代から変わっていないが、電源ユニットは毎年のように新製品が登場し、中身も確実に進化している。
その理由の一つにはPCパーツの進化がある。CPUやGPUの性能が向上するとともに消費電力も増大し、必要な電力仕様も変化してきた。総合出力が大きくなっただけでなく、必要とされる電圧も+3.3Vや+5Vから+12Vへとシフトし、電源ケーブルやコネクタの仕様もそれに合わせて追加、更新されてきている。
ここ1年ほどの間にも6コアCPUやGeForce GTX 480など消費電力の大きなパーツが登場してきており、これらを組み合わせたシステムに対応できる大出力電源のバリエーションも増加。また、大出力となる+12V系は安全規格などへの配慮から複数の系統に分けられていることが多かったが、オーバークロック環境やハイエンド構成では1系統ごとの制限が原因でトラブルになる例もあることから、+12V系を1系統にまとめた製品も増加傾向にある。
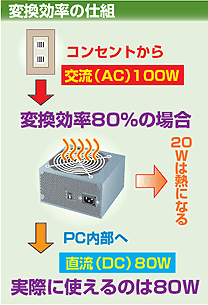
高変換効率の電源は発熱が小さい
効率が80%ということは、入力された交流が100Wなら80Wの直流を作れるということだ。残りの20Wは熱になる。効率70%の電源でこれと同じ80Wの直流を作る場合に必要な交流は114W(≒80W÷0.7)で、発熱も34Wと大きくなる
電源を購入するときはここをチェック!
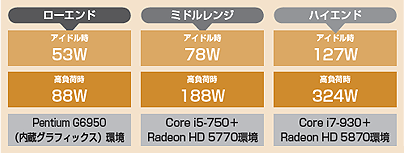
クラス別に消費電力を実測した。高負荷時の消費電力が電源出力にとっての100%では負担が大き過ぎるので、70%前後くらいが無難。たとえば、ハイエンド構成なら324W÷0.7≒463W以上、+12V系だけでこれくらいの電力が供給できることが目安。総合出力では500~650Wクラスの電源が適切と言える
【1】定格出力
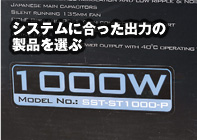
PCが必要とする電力量に対して少な過ぎるのはもちろん、多過ぎてもよくない。適切な出力の電源ユニットを使うことが何よりも重要である
【2】ファン径・回転数
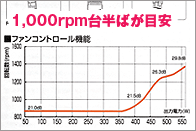
12cm角以上の大型ファンは低速でも風量が稼げる。2,000rpm近くになると音が耳に付くので高負荷時でも1,600rpm前後の製品が望ましい
【3】変換効率
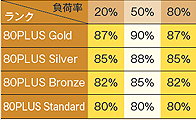
80PLUS認証を受けるには定められた変換効率を満たす必要がある。今なら最低でも80PLUSは必須、予算内でできるだけ上位ランクを狙いたい
【4】品質・信頼性

コンデンサの品質は安定性や寿命に直結する。よいコンデンサであることに越したことはない。品質重視なら3年以上の長期保証も条件にしたい
80PLUS Gold認証製品が増加
変換効率という指標が定着
静音ニーズも電源ユニットの進化を促してきた大きな要素だが、それに関連して、電源選びの大きな要素として定着してきたのが変換効率だ。交流を各系統の直流に変換する際にいかにロスなく変換できるかを示す要素で、変換効率の高さは消費電力の低さ、発熱の小ささに直結し、静音性の向上にもつながる。最近の製品はこの変換効率の進化が目覚ましい。
これには「80PLUS」の存在が大きい。「80PLUS」は、環境保護の観点から作られた業界団体による認証プログラムだが、電源ユニットの変換効率はスペックだけではなかなか分かりにくいだけに、業界団体の「お墨付き」である80PLUSが、製品選びの指標として大きく浸透したのだ。
信頼性、長寿命といった要素もこれまでと変わらず重要。これらを大きく左右する電源ユニットの品質は搭載コンデンサや変換効率などが一つの目安にはなるが、内部設計や出力電圧の安定性など、実際に検証しなければ分からないこともある。本特集ではそういった部分に関しても、内部写真を紹介しつつ、検証を行なっているので、参考にしてほしい。
内部ケーブルにも注目

ケーブル/コネクタに関する仕様も製品ごとに違いがある部分で、見逃せない要素と言える。着脱式のプラグイン方式は厳密に突き詰めればコネクタ部の電気的なロスがないとは言えないが、必要なケーブルだけを選んで使え、作業がしやすくなるというメリットは大きい。また、スリム仕様のケーブルを採用するなど扱いやすさをより向上させた製品もある。なお、最近はマザーボードベース裏面を使った配線に対応するPCケースが多いが、そういったPCケースで使う場合はケーブルの長さも重要になるため、前もって確認しておこう。
【検証環境】HDD:Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS(Serial ATA 2.5、7,200rpm、1TB)、電源:Corsair Memory CMPSU-850TXJP、OS:Windows 7 Ultimate 64bit版、[ローエンド]CPU:Intel Pentium G6950(2.8GHz)、マザーボード:GIGABYTE GA-H55-USB3(rev. 1.0)(Intel H55)、メモリ:センチュリー CK2GX2-D3U1333(PC3-10600 DDR3 SDRAM 2GB×2)、[ミドルレンジ]CPU:Intel Core i5-750(2.66GHz)、マザーボード:ASUSTeK P7P55D-E EVO(Intel P55)、メモリ:センチュリー CK2GX2-D3U1333(PC3-10600 DDR3 SDRAM 2GB×2)、ビデオカード:玄人志向 RH5770-E1GHD/DP/G3(Radeon HD 5770)、[ハイエンド]CPU:Intel Core i7-930(2.8GHz)、マザーボード:MSI X58A-GD65(Intel X58+ ICH10R)、メモリ:Corsair Memory CMX8GX3M4A1600C9(PC3-12800 DDR3 SDRAM 2GB×4 ※3枚使用)、ビデオカード:MSI R5870 Lightning(Radeon HD 5870)


















