|
|
||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||
| TEXT:鈴木雅暢 | ||||||||||||||||||||||||
| 第2世代製品の台頭で市場はさらにヒートアップ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
 速くて静かで省電力、しかも衝撃や振動にも強い次世代ストレージとして注目を集めるSSDだが、過渡期の製品だけに混乱要素も多く持っている。本特集では最新SSDの実力検証や活用法の紹介とともに、未解明の部分にも切り込んでいく。
速くて静かで省電力、しかも衝撃や振動にも強い次世代ストレージとして注目を集めるSSDだが、過渡期の製品だけに混乱要素も多く持っている。本特集では最新SSDの実力検証や活用法の紹介とともに、未解明の部分にも切り込んでいく。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 新世代のストレージとして台頭著しいSSD(Solid State Drive)。ここ1年ほど常に自作市場の話題の中心にいた印象があるが、ここに来て第2世代SSDの価格が下落。さらなる盛り上がりを見せつつある。SSDのサポートを強化したWindows 7の登場も間近に控えており、これからはいよいよ本格的な普及段階に入りそうな気配も予感させる。そろそろHDDや光学ドライブなどと同じように一般的なPCパーツとして、強く意識していく段階に入ってきたと言える。 SSDは、記憶媒体として半導体メモリを利用したストレージデバイスだ。基板に半導体のフラッシュメモリチップを実装しただけのシンプルな構造で、メモリにかける電圧を制御するだけでデータの読み書きを行なうことができる。HDDのモーターやアームのように機械で動作する部品を持たないことから、消費電力や発熱はHDDよりもずっと低く、動作音もゼロ。動作中の振動や衝撃にも強いというメリットがある。 そして、最大のメリットと言えば、まず圧倒的な速さが挙げられる。黎明期のSSDは弱点もある製品が多かったが、現在主流の第2世代のSSDはもはや速度面でHDDに劣る部分は何もない。リード/ライト、シーケンシャル/ランダムの区別なく、すべてにおいてHDDを圧倒するパフォーマンスを誇る。とくに日常操作の体感速度に影響するランダムアクセスの性能はHDDの数倍~数十倍にも上り、HDDからSSDへ乗り換えたなら、体感でもレスポンスの違いをはっきりと感じ取ることができるだろう。 一方で、デメリットとしては、HDDに比べて容量が小さく、導入コストが割高なことが挙げられる。安くなったとはいえ、64GBで1.5万円以上もする。HDDなら1TBモデルを2台買ってもお釣りが来るだけに、その差は明らかである。ただ、SSDの価格自体は発売当時と比べてかなりのスピードで値下がりが進んでおり、1GBあたりの容量単価も改善が進んでいる(それでもまだHDDと比較すると非常に高いが)。下に2008年9月に発売されたIntelのX-25Mの80GBモデルの価格変動をグラフにしたが、発売当時の価格と比べると、現在は実に1/3以下にまで値下がりしている。SSD市場全体を見ると大容量化も進んでいるので、価格容量比はこれからも早いペースで改善していくだろう。 なお、SSDが本格的にストレージデバイスとして利用されるようになったのはここ1、2年のことであり、未知数の部分も残されている。今後、予期しなかったようなトラブルが起こる可能性もなくはないと言える。 |
||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||
| ※AKIBA PC Hotline!調べ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
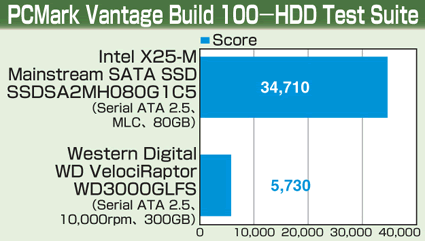 |
||||||||||||||||||||||||
| 圧倒的な高性能 もはやHDDとは比べ物にならない圧倒的なパフォーマンスがSSDの最大の魅力。とくにランダムアクセス性能に優れ、キビキビとしたレスポンスの速さは明らかに体感できるほど |
||||||||||||||||||||||||
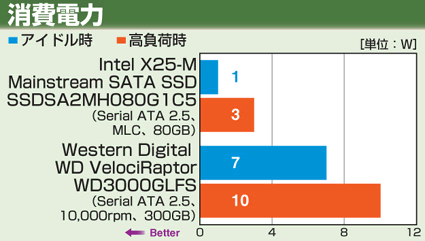 |
||||||||||||||||||||||||
| 省電力で発熱も小さい 負荷時で2、3W、アイドル時はわずか1、2Wと消費電力特性も実に優秀だ、モーターやアームなどの機械部品が必要ないアドバンテージは大きい。当然、騒音もゼロだ |
||||||||||||||||||||||||
| 【検証環境】 CPU:Intel Core 2 Duo E6600(2.4GHz) マザーボード:ASUSTeK P5Q(Intel P45+ICH10R) メモリ:ノーブランド PC2-6400 DDR2 SDRAM 1GB×2 ビデオカード:NVIDIA GeForce 8600 GTリファレンスカード システムHDD:日立GST Deskstar T7K500 HDT725025VLA380(Serial ATA 2.5、7,200rpm、250GB) OS:Windows Vista Ultimate SP1 高負荷時:PCMark Vantage Build 100実行時 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 実際、これまでにも市場への普及以前には予想されていなかった事象がいくつか浮上している。その代表的なものが、いわゆる「プチフリ」と呼ばれる、低価格SSDに見られるレスポンス低下現象だ。これは主にコントローラにJMicronのJMF602を搭載した低価格SSDにおいて、書き込みが集中するような状況で起きることが分かってきたことから、この「プチフリ」をきっかけにコントローラチップの種類やキャッシュ容量に注目が集まるようになった。JMF602に代わり「プチフリしないコントローラ」として台頭してきたのがIndilinxのBarefootで、「第2世代のSSD」と言えば、これを搭載した製品群が中心だ。だが、プチフリ騒動の後も「使い込んでいくとベンチマークテストの数字が悪くなる」などの問題が浮上。さらにこれに関連して、デフラグに関しても情報が錯綜してきている。 使い込みによる速度低下は実際に起きるのか起きないのか、その対策や予防法はあるのか。そして、デフラグはしたほうがよいのか、しないほうがよいのか。新製品の登場などで盛り上がりを見せる一方で、現在のSSD市場は過渡期ならではの問題点や曖昧な情報などの混乱要素が一気に噴出し、入り組んだ状況にあると言える。本特集ではそれらを理解するのに有用なSSDの仕組を解説するとともに、情報を整理。実際に検証も交えて、それらの不明瞭になっている部分と一つ一つ向き合って明らかにしていきたい。 |
||||||||||||||||||||||||
| 現在リリースされている主なSSDコントローラ一覧 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ※公称速度はJMF602を除きMLC使用時のもの | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
サイト内検索
DOS/V POWER REPORT 最新号
-

-
DOS/V POWER REPORT
2024年冬号発売日:12月28日
特別定価:2,310円
書籍(ムック)

-
PC自作・チューンナップ虎の巻 2023【DOS/V POWER REPORT特別編集】
発売日:2022/11/29
販売価格:1,800円+税

-
このレトロゲームを遊べ!
発売日:2019/05/29
販売価格:1,780円+税

-
特濃!あなたの知らない秋葉原オタクスポットガイド
発売日:2019/03/25
販売価格:1,380円+税

-
わがままDIY 3
発売日:2018/02/28
販売価格:980円+税

-
忍者増田のレトロゲーム忍法帖
発売日:2017/03/17
販売価格:1,680円+税

-
楽しいガジェットを作る いちばんかんたんなラズベリーパイの本
発売日:2016/09/23
販売価格:2,400円+税

-
DVDで分かる! 初めてのパソコン自作
発売日:2016/03/29
販売価格:1,480円+税

-
ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』2
発売日:2015/12/10
販売価格:1,280円+税

-
髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 風雲編
発売日:2015/06/29
販売価格:2,500円+税

-
髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 怒濤編
発売日:2015/06/29
販売価格:2,500円+税

-
わがままDIY 2
発売日:2015/02/27
販売価格:980円+税

-
ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』
発売日:2014/12/05
販売価格:1,280円+税
-

-
わがままDIY 1
発売日:2011/12/22
販売価格:980円+税
アンケートにお答え頂くには「CLUB IMPRESS」への登録が必要です。
*プレゼントの対象は「DOS/V POWER REPORT最新号購入者」のみとなります。
ユーザー登録から アンケートページへ進んでください

 10月に発売が迫っているMicrosoftの次期OS「Windows 7」ではHDDとは区別され、「SSD」として扱われる。性能向上や寿命延長のためにOSがSSDに対して不要な領域を通知するTrimコマンドの実装など、管理が最適化され、より快適に使えるようになると期待されている。
10月に発売が迫っているMicrosoftの次期OS「Windows 7」ではHDDとは区別され、「SSD」として扱われる。性能向上や寿命延長のためにOSがSSDに対して不要な領域を通知するTrimコマンドの実装など、管理が最適化され、より快適に使えるようになると期待されている。
