| その他の特集(2011年) | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
||||||||||||||
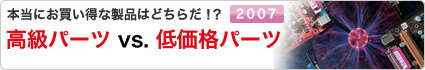 |
||||||||||||||
| TEXT:橋本新義 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
 PCパーツの価格と性能を考える際、メモリは特殊な存在だ。ノーブランド品が多く流通していたり、価格が大きく変動したりと、ほかのパーツにはない事情があるためだ。メモリの価格差はどういう点に影響するのだろうか。 PCパーツの価格と性能を考える際、メモリは特殊な存在だ。ノーブランド品が多く流通していたり、価格が大きく変動したりと、ほかのパーツにはない事情があるためだ。メモリの価格差はどういう点に影響するのだろうか。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 定格性能を見る | ||||||||||||||
| メモリの場合、速度に関するパラメータ(=動作クロックとアクセスタイミング)が規格で規定されている。こうした事情から、高級製品であろうと低価格製品であろうと同じクロックとアクセスタイミングであれば、理屈の上から言えば速度差はほぼないはずである。 そこでまずは、用意した3種類のPC2ー6400 DIMM(DDR2-800メモリ)と、1,250MHz動作のオーバークロックメモリCorsair Memory「DOMINATOR」の計4機種で、デュアルチャンネル時の定格動作での速度差を測定してみた(DOMINATORは定格設定が1,250MHz動作のため、マザーボードでのデフォルト設定である800MHz動作で測定)。 ベンチマークのタイトルおよびテスト項目は、本誌ではおなじみとなるPCMark05の「Memory Test Suite」だ。実際の結果は下のグラフを見てほしいが、ほぼ理屈どおりの結果となった。動作クロック800MHz同士の比較ではほとんど性能差はない。定格で使う分にはメモリ価格による性能差は存在しないと言ってよいだろう。 |
||||||||||||||
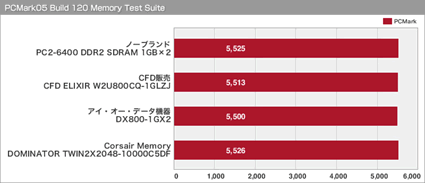 |
||||||||||||||
| 【検証環境】 CPU:Intel Core 2 Duo E6700(2.66GHz) マザーボード:ASUSTeK P5B Deluxe/WiFi-AP(Intel P965) ビデオカード:MSI RX1650XT-T2D256E(AMD Radeon X1650 XT) HDD:Maxtor DiamondMax 10 6L250S0 (Serial ATA、7,200rpm、250GB) OS:Windows Vista Ultimate |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ノーブランド | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 実売価格:7,000円前後 | ||||||||||||||
| 問い合わせ先:なし URL:なし |
||||||||||||||
 メモリチップに「Mr.Stone」の刻印がなされた、低価格なノーブランドDDR2-800メモリ。基板はA-DATA製品と同等の、台湾BrainPowerの手によるJEDEC準拠品を使用している。 メモリチップに「Mr.Stone」の刻印がなされた、低価格なノーブランドDDR2-800メモリ。基板はA-DATA製品と同等の、台湾BrainPowerの手によるJEDEC準拠品を使用している。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Corsair Memory | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 実売価格:100,000円前後(2本セット) | ||||||||||||||
| 問い合わせ先:info@synnex.co.jp(シネックス) URL:http://www.corsairmemory.com/ |
||||||||||||||
 オーバークロックメモリの中でも最高速の、1,250MHz動作(EPP対応マザー使用時)を実現した製品。特殊な放熱構造を備える基板とヒートシンクに加え、冷却ファンも付属する。 オーバークロックメモリの中でも最高速の、1,250MHz動作(EPP対応マザー使用時)を実現した製品。特殊な放熱構造を備える基板とヒートシンクに加え、冷却ファンも付属する。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
 |
||||||||||||||
| オーバークロック耐性は? | ||||||||||||||
| 定格性能対決では、メモリにおいて価格差と性能差は必ずしも直結しないことが改めて確認できた(ただし、オーバークロックメモリとそれを活かせるマザーボードの場合は例外である)。 では、メモリの価格差に直結する要素は何だろうか? ある程度知られているものとしては、定格動作環境より厳しい条件で動作させた際の安定性がある。ブランド品メモリの多くはノーブランド品の数倍の手間をかけて厳しい動作試験を実施しているため、より悪条件に強い傾向がある(もちろん、例外は存在するが)。ここでは、PCにおける定格以上に厳しい動作条件の一つとして、オーバークロック(OC)耐性をテストしてみた。 テスト内容は、BIOS設定でシステムクロック(ベースクロック)を操作し、Windows Vistaの起動とCPU-Zによるメモリ設定状態の確認作業までを完走できるクロックの限界を探るというもの(Corsair Memory DOMINATORのみ、システムクロックとメモリクロックの比率を1:1とする設定を追加している)。メモリ電圧は、DOMINATORは定格の2.4V、そのほかは自動設定。アクセスタイミングも自動設定だが、Windows起動後、CPU-Zにて定格と同じであることを確認している。 一般的にOC耐性テストは「特定のベンチマークテストを完走できるレベル」が基準に使われるが、今回はそれよりも負荷が軽い点には注意されたい。 さて、結果としては、少し意外なものとなった。OCメモリのDOMINATORが圧倒的トップである点は予想のとおりだったのだが、続く2位にノーブランドメモリが入ったからである。筆者の過去の経験でも、ノーブランドメモリには非常にOC耐性の高いものがまれに存在していたが、今回のものはそうした“当たり”の製品と思われる。ただし、同じチップを使っていても、ロットが違うと特性がまったく違ってくることがあるので、耐性の高いバルクメモリを見分けるのは難しい。 |
||||||||||||||
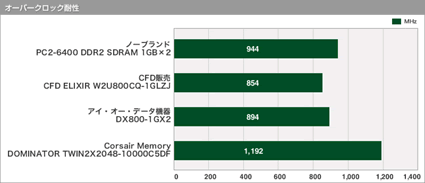 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
サイト内検索
DOS/V POWER REPORT 最新号
-

-
DOS/V POWER REPORT
2024年冬号発売日:12月28日
特別定価:2,310円
書籍(ムック)

-
PC自作・チューンナップ虎の巻 2023【DOS/V POWER REPORT特別編集】
発売日:2022/11/29
販売価格:1,800円+税

-
このレトロゲームを遊べ!
発売日:2019/05/29
販売価格:1,780円+税

-
特濃!あなたの知らない秋葉原オタクスポットガイド
発売日:2019/03/25
販売価格:1,380円+税

-
わがままDIY 3
発売日:2018/02/28
販売価格:980円+税

-
忍者増田のレトロゲーム忍法帖
発売日:2017/03/17
販売価格:1,680円+税

-
楽しいガジェットを作る いちばんかんたんなラズベリーパイの本
発売日:2016/09/23
販売価格:2,400円+税

-
DVDで分かる! 初めてのパソコン自作
発売日:2016/03/29
販売価格:1,480円+税

-
ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』2
発売日:2015/12/10
販売価格:1,280円+税

-
髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 風雲編
発売日:2015/06/29
販売価格:2,500円+税

-
髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 怒濤編
発売日:2015/06/29
販売価格:2,500円+税

-
わがままDIY 2
発売日:2015/02/27
販売価格:980円+税

-
ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』
発売日:2014/12/05
販売価格:1,280円+税
-

-
わがままDIY 1
発売日:2011/12/22
販売価格:980円+税
アンケートにお答え頂くには「CLUB IMPRESS」への登録が必要です。
*プレゼントの対象は「DOS/V POWER REPORT最新号購入者」のみとなります。
ユーザー登録から アンケートページへ進んでください



 今回使ったDOMINATORなどOC用メモリの一部には、「EPP」と呼ばれるOCメモリの半自動設定機能に対応した製品がある。対応メモリとマザーボード環境で、OCメモリ側に合わせたシステムクロックや電圧などが自動設定されるという仕組だ。ただ、CPUのシステムバスよりもメモリのクロックが高い場合、自動でCPUの耐性を超えた設定がなされて起動できなくなることがあるので、EPPを有効にする際は、同時にCPUのクロック倍率を最小に下げておくのがコツだ。今回はGIGABYTE GA-M59SLI-S5とDOMINATORを使い、CPUのOC設定を0%と最高(MAX)の2パターンに設定してテストしたところ、定格の1,250MHzまでは上昇しなかったが、0%で1,090MHz、MAXで1,120MHzとメモリクロックが高速化された。
今回使ったDOMINATORなどOC用メモリの一部には、「EPP」と呼ばれるOCメモリの半自動設定機能に対応した製品がある。対応メモリとマザーボード環境で、OCメモリ側に合わせたシステムクロックや電圧などが自動設定されるという仕組だ。ただ、CPUのシステムバスよりもメモリのクロックが高い場合、自動でCPUの耐性を超えた設定がなされて起動できなくなることがあるので、EPPを有効にする際は、同時にCPUのクロック倍率を最小に下げておくのがコツだ。今回はGIGABYTE GA-M59SLI-S5とDOMINATORを使い、CPUのOC設定を0%と最高(MAX)の2パターンに設定してテストしたところ、定格の1,250MHzまでは上昇しなかったが、0%で1,090MHz、MAXで1,120MHzとメモリクロックが高速化された。
